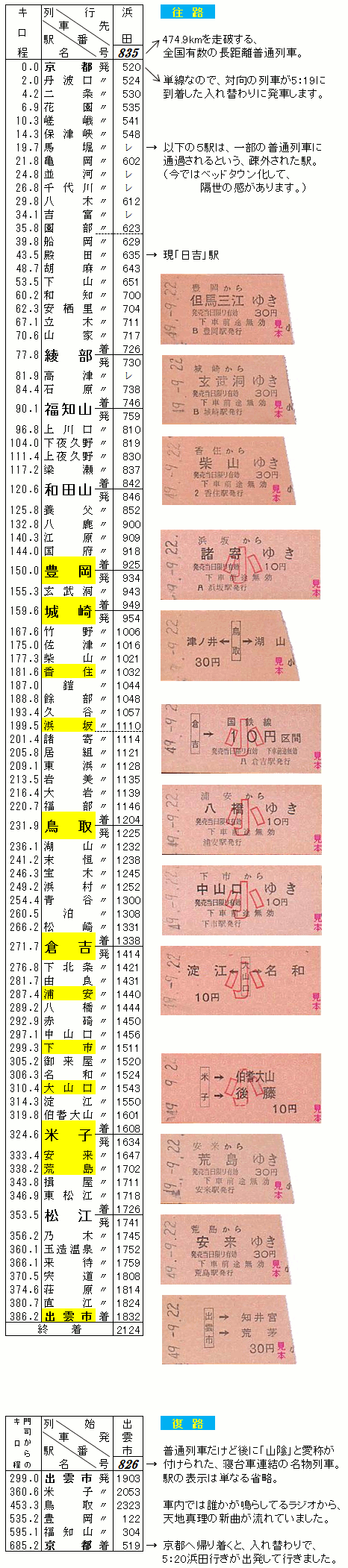※ このページは、主要部の字が小さいため、スマホ横向けでのご覧をお勧めします。
当時収集対象としていた10円の小児専用券というのは、都市部では(自動券売機なしが前提ですが)普通にありましたが、
山陰線のような人口密度の低い地域、且つ幹線(これ多分重要)には、無いことの方が多く、大人券の右端を斜めに切り取る対応でした。
私はこれを収集分類上、勝手に2級品扱いしていました。
さて最後の収集行ですが、普通列車は主要駅では大概、数分~20分程度停車するため、余裕で出札口往復が出来ました。
しかしこの2級品を出す駅の多いこと!
むしろ普通列車しか停車しない小駅の方が、小児専用券を在庫していたように思えます。恐らく、主要駅では幹線ならではの、
優等列車用切符の充実を優先させていたものと思われます。
また、この「10円」というのは当時5km以内に適用される運賃でした。
隣駅への距離が5kmを超えるというのは、これも都市部ではあまり考えられませんが、地方では結構ありました。(20円券は収集対象外でした)
このように、収集には不利な条件が揃ったこの時の旅は、振り返ってみると長距離乗車が無意識的な目的だったようにも思えてきます。
今で言う「乗り鉄」に通じる部分が有ったのかも知れません。
下は、往路の全駅時刻表と、復路の超省略時刻表です。
切符の日付が当時の記憶を呼び起こしてくれます。13歳の秋でした。